クラブ活動の様子 バトントワリング部2011年06月23日 19:27
中高バトントワリング部の様子を紹介します。今年も全国大会を目指し、今はボディワーク(体力作り)や基礎技術の向上に励んでいます。 夏休みの練習や合宿では、チームづくりに時間を割き完成度の高い演技を目指します。ちょうど1年前に入部した中学2年生はこの1年間、一生懸命に練習した成果もあり、とても上達しました。
夏休みの練習や合宿では、チームづくりに時間を割き完成度の高い演技を目指します。ちょうど1年前に入部した中学2年生はこの1年間、一生懸命に練習した成果もあり、とても上達しました。
9月に行われる文化祭でもバトントワリングの演技がありますのでぜひご覧になって下さい。
« 2011年05月 | メイン | 2011年07月 »
中高バトントワリング部の様子を紹介します。今年も全国大会を目指し、今はボディワーク(体力作り)や基礎技術の向上に励んでいます。 夏休みの練習や合宿では、チームづくりに時間を割き完成度の高い演技を目指します。ちょうど1年前に入部した中学2年生はこの1年間、一生懸命に練習した成果もあり、とても上達しました。
夏休みの練習や合宿では、チームづくりに時間を割き完成度の高い演技を目指します。ちょうど1年前に入部した中学2年生はこの1年間、一生懸命に練習した成果もあり、とても上達しました。
9月に行われる文化祭でもバトントワリングの演技がありますのでぜひご覧になって下さい。
今回は高1の国語総合の様子を紹介します。
今日の授業では『徒然草』第141段「非田院尭蓮上人は」の読解を行いました。中学時代に先取り学習として古典文法の用言を学習しているため、高校ではさらに助動詞の学習を進めています。授業に臨むにあたって家庭で予習をしています。授業の中では文法に限らず登場人物の心情や時代背景まで探究を深め、古典文学の真髄に触れているようでした。



オーストラリアにあるSt. Catherine’s高校との交換留学プログラムへの参加生徒を募集しています。St. Catherine’s高校はメルボルンにある名門女子校で、毎年大妻高校との交換留学制度を設けています。
大妻生2名は夏にSt. Catherine’s高校へ留学し、現地家庭へホームステイをします。冬にはSt. Catherine’s生2名が大妻を訪問し、同じくホームステイを通じて日本文化を学びます。このプログラムに参加した大妻生は毎年国際理解を深め、広い視野持って日本に戻ってきます。意欲ある大妻生の参加をお待ちしています。
・期間:平成23年夏休み 3週間~1か月(応相談)
・資格:①本校高校1年生、もしくは高校2年生であること。
②国際理解に興味があり、一定の成績を修めていること。
③原則として冬にSt. Catherin’s生の預かりが可能なことが望ましいが、留学のみでも可。
・締切:平成23年6月27日(月)
担任の先生を通じて国際理解教育担当者まで。
6月11日(土)、毎年恒例の「先輩を囲む会」が文系131名・理系99名の計230名を集め、会議室とカフェテリアにおいてそれぞれ行われました。震災の影響で3月の合格報告会が中止になったことも関係して、この会への期待が大きかったようです。
大学一年生と教育実習生の先輩方のほか、昨年と同様、すでに就職した社会人の先輩を含め12名の先輩方に講演していただきました。これは、現役の生徒たちに、単なる受験勉強にとどまらない、長期的な視野から自らの進路を考えるきっかけになったはずです。
入学して二か月の大学一年生からは、キャンパスライフの楽しさはもちろん、入学後の勉強でも充実している様子が伝わり、一日一日を大切にすること、授業も部活動も100%力を尽くすこと、などの意欲的な姿勢が伝わってきました。
 「基礎が大切」「学校の小テストにも真面目に取り組め」「学校での予習・復習の大切さ」「ポジティブ・シンキング」など、先輩たちが受験勉強を通じて後輩に伝えたいメッセージが熱く語られました。その中でも、「目指さないと到達できない」と自らの目標を高く設定して努力することの大切さを語った先輩の話や、「6年間部活動を続けることが、受験勉強で最後まであきらめない精神力を養成した」と部活動と勉強を両立させた先輩の言葉が印象的でした。具体的な勉強法としては、「ストップウォッチを使って勉強時間を管理する方法」「日本史では系図を大きな紙に書いて関連事項を書き込む」などが紹介され、会の終了後の個別相談では、先輩たちが実際に作成したノートや図表が展示され大好評でした。
「基礎が大切」「学校の小テストにも真面目に取り組め」「学校での予習・復習の大切さ」「ポジティブ・シンキング」など、先輩たちが受験勉強を通じて後輩に伝えたいメッセージが熱く語られました。その中でも、「目指さないと到達できない」と自らの目標を高く設定して努力することの大切さを語った先輩の話や、「6年間部活動を続けることが、受験勉強で最後まであきらめない精神力を養成した」と部活動と勉強を両立させた先輩の言葉が印象的でした。具体的な勉強法としては、「ストップウォッチを使って勉強時間を管理する方法」「日本史では系図を大きな紙に書いて関連事項を書き込む」などが紹介され、会の終了後の個別相談では、先輩たちが実際に作成したノートや図表が展示され大好評でした。

教育実習生や社会人の先輩からは、大学と職場の設備や雰囲気の紹介のほか、「高校卒業までの間にすべきこと」「視野を広げて考えること」「生徒会役員での経験が全体を統括する仕事に役立っていること」など充実した高校生活を送ることが大切だというアドバイスがありました。
また、社会人の先輩の話が印象的だったというアンケート結果もあり、その中で、進路を考える時に「ぶれない自分の軸」を持つことの大切さが多くの共感を得たようでした。「ハンディキャップを持った人々に役に立ちたい」という自分の軸が、高校1年生の時は医学部への志望となり、実際は学校行政からそれを支援する教育学部への進学に変わり、教育学部在学中のインターシップの経験から社会インフラを得意とする企業への就職と、志望学部や職業選びが途中で大きく変化したが、自分の軸はぶれなかったという話が、在校生に本当の意味で“進路を考える”とはどういうことなのかということを学ぶ大きな機会となりました。
 また、もうひとりの社会人の先輩からは、近年の物性物理学において最も刺激的な分野の1つとなっている“ソフトマター物理学”を大学・大学院時代に研究テーマに選んだいきさつや、現在、大学の研究所で技術系職員として高度な実験のサポートを行う職務に従事していることなどが話されました。技術系職員の仕事だけでなく、研究者の卵として研究を現在も続けていることや、その研究が研究所の“所長賞”を受賞したことなど日々努力を継続している先輩の姿に耳を傾けていました。彼女が語る「研究者(科学者)の実像」「学会や国際会議の様子」「研究はボーダレスで英語が共通語」といった話は、研究者を目指す後輩たちに大きな刺激となったようです。
また、もうひとりの社会人の先輩からは、近年の物性物理学において最も刺激的な分野の1つとなっている“ソフトマター物理学”を大学・大学院時代に研究テーマに選んだいきさつや、現在、大学の研究所で技術系職員として高度な実験のサポートを行う職務に従事していることなどが話されました。技術系職員の仕事だけでなく、研究者の卵として研究を現在も続けていることや、その研究が研究所の“所長賞”を受賞したことなど日々努力を継続している先輩の姿に耳を傾けていました。彼女が語る「研究者(科学者)の実像」「学会や国際会議の様子」「研究はボーダレスで英語が共通語」といった話は、研究者を目指す後輩たちに大きな刺激となったようです。
予定時間を過ぎ、会の終了後も、2時間近く受験生の個別相談をしてくれた先輩たちもいて、充実した会となったと同時に、卒業生の母校への愛校心を再確認した行事となりました。
大妻中高では水曜日の6時間目は、全学年ともHRの時間です。6月8日(水)の6時間目、中学1年生は9月末の文化祭へ向けての準備を本格的に開始しました。
中学1年生の今年の文化祭展示テーマは「大妻中学校の紹介」。訪れる小学生たちに本校の魅力を伝えようというもので、1年前2年前の自分たちの姿を思い返しながら取り組みはじめました。この日は、あらかじめ各自が考えてきた、「小学生のときに知りたかったことや不安だったこと」「ぜひ伝えたい大妻中高の魅力」を互いに発表しあいました。各クラス2名の文化祭企画委員は、全体に説明をしたあと、それぞれの班の進行状況を見て回り、まとめ方のアドバイスをするなど大忙しでした。「部活動や年間行事のことを紹介したい」「入学式から10日間の自分たちの生活を発表したら面白いんじゃないか」「震災の日のことを上級生や先生から聞いて、防災のことについて発表するのはどうか」などなど、活発に意見が交わされていました。アイディアを書いた付箋を模造紙に整理しながら、考えを広げることができたようです。
ここで出されたアイディアをもとに、7クラスがそれぞれ違った角度から大妻中学校を紹介する展示発表を作っていきます。中学1年生の創意工夫に、どうぞご期待ください!
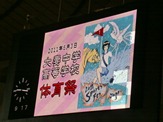
電力量の制限により,例年よりも短縮した形の体育祭となってしまいましたが,その分密度の濃い競技内容と体育館いっぱいにこだまする応援の声により,例年に負けないくらい盛り上がっておりました。
応援団も限られた練習量ではありましたが,体育祭の花形として,先輩たちが今まで培ってきた伝統に新たな1ページを刻む堂々とした応援を見せてくれました。その雄姿に感動したという生徒も多かったようです。

初めての体育祭を経験した中学1年生は,開会式の行進に戸惑いながらも,一生懸命に大妻の体育祭を肌で感じ,楽しんでいるようでした。
白熱した戦いを終えた生徒たち全員が充実した表情で迎えた閉会式。中高全員の生徒が一堂に会する機会は他にありません。その全員で歌った校歌はいつまでも耳に残るものになりました。これからも大妻の伝統を受け継ぎつつ,さらなる発展を期待したいと思います。体育祭の開催にあたり,たくさんの皆様方からご協力をいただきました。この場を借りて厚く御礼を申し上げます。
たくさんのご来場をいただきまして,誠にありがとうございました。



6月2日(木),代々木第一体育館にて翌日3日に行われる体育祭のリハーサルが行われました。残念ながら今年度は節電の影響により,プログラムを縮小して行わざるをえない状況になってしまいましたが,応援合戦など体育祭の華は健在です。特に高校3年生は最後の体育祭に向けて,準備も真剣に行っていました(右下写真は放送席)。
明日の晴れの舞台をどうぞお楽しみに!受験生の保護者の皆さまもどうぞ。お待ちしております。


